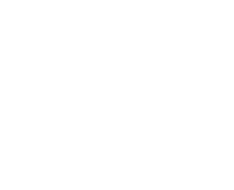農園だよりDiary
2025年10月
2025.10.08
皆さん今日は。
まだまだ暑い夏が続いている日本列島ですが皆様いかがお過ごしですか。我が家の稲刈りは9月6日から始まり9月16日に終えることが出来ました。例年なら秋雨前線が通過する時期で稲刈り期間中に雨の日もあるのですが、今年は前線が居座りなかなか晴天が続きませんでした。コンバインでの稲刈りは稲が濡れているとコンバインの機体の中で藁や籾がスムーズに流れずトラブルの元なので朝露が落ちた頃からしか作業が始められません。いざ作業開始、ところが雨。こんな日が幾日も。また収穫初めの頃の籾の水分は30%弱あるのですが日が経つにつれ乾燥し最後の頃には20%くらいに下がるのが例年です。今年は最後の稲刈りまで水分が下がりませんでした。米の保存のためには15%以下まで乾燥させなければなりません。乾燥温度を上げると時間は短縮できるのですが高温乾燥は食味が落ちるので時間をかけてゆっくり乾燥。すると乾燥機が空かないので稲刈りができません。適期刈り取りの為に、朝露がまだ落ちる前から機械に詰まらないよう低速でゆっくり刈り取りとか乾燥機が夕方に空くのに合わせてコンバインにライトを点けて刈り取りとかちょっとした時間を見つけての作業でした。苦労のかいあって適期に刈り取りでき、良いお米が収穫できました。
連日報道されているお米問題。政府は備蓄米放出とアメリカ米の輸入前倒し。民間では外国米輸入。農水大臣は米流通を「市場にジャブジャブ」という表現を使い価格を下げる政策をとると発言しました。「平成のコメ騒動」から30年。米価格は年々下がり、米作りは自給0円と言い表されました。価格が安い時には国は「市場原理」と傍観し、価格が上がると備蓄米、破格の2000円での放出で市場介入。今頃になって減反政策は間違い、コメ増産と言います。今回の米騒動は国内の「需要量と供給量の実像」が把握できていなかったとうお粗末な事が原因のようですが、農家にとって供給過剰は安値、豊作貧乏につながり困ったことです。だから国が進める「市場原理」の中では何の保証もないのに余るようには作れなかったのです。
私はNHKテレビ「映像の世紀」をよく見ます。映像技術が開発され、発展していく過程でこれまで撮影され、保存されてきた映像がテーマに沿って放送されます。「歴史は繰り返す」の言葉通り私たちの身の回りで起きている現象が過去の映像の中に現れています。よく放送されるナチスドイツ。占領した国から収奪した農産物を、また若い労働者をドイツ本国に送り、国民は働かずして豊かな生活を享受する様子が流れます。日本でも高度経済成長と言われた時代、地方農村の若者が安価な労働力として、また季節出稼ぎ労働者が都会に流れることで、経済が成長しました。日本では1960年代、ついこの前まですべての国民に米が行き渡らず、「貧乏人は麦を食え」という時代だったのが、豊かになり、パンや麵を食べるようになると米は余るようになりました。国は市場経済に委ねるとして米流通から手を引き、「民間自立」の時代になりました。全国各産地は米が余って売れない中で収量が多い品種を捨て、味が良い品種を作り「どうぞうちの米を買ってください」と頭と価格を下げて商売をしてきたのがこの30年です。ドイツに占領された国は食料を、また来年撒く種まで収奪されました。現代日本では買い手市場の中で地方農村は体力を奪われ老夫婦の生活が精いっぱい。後継者を育てる力など残っていないのです。社会的強者と弱者の関わり合いの中で生産現場を知らない「都会の民」の生活の為に「農村の民」は収奪されSDGsの時代にコメ生産農家は消滅危惧種になろうとしているのが現実です。
我が家の菜園では沢山の生き物がそれぞれけん制しあいながらもバランスよく暮らし、野菜は健康に育っています。人間の世界でもそれぞれの生存を尊重しあうことが明日の自分の生存につながる最低限の姿勢ではないでしょうか。
まだまだ暑い夏が続いている日本列島ですが皆様いかがお過ごしですか。我が家の稲刈りは9月6日から始まり9月16日に終えることが出来ました。例年なら秋雨前線が通過する時期で稲刈り期間中に雨の日もあるのですが、今年は前線が居座りなかなか晴天が続きませんでした。コンバインでの稲刈りは稲が濡れているとコンバインの機体の中で藁や籾がスムーズに流れずトラブルの元なので朝露が落ちた頃からしか作業が始められません。いざ作業開始、ところが雨。こんな日が幾日も。また収穫初めの頃の籾の水分は30%弱あるのですが日が経つにつれ乾燥し最後の頃には20%くらいに下がるのが例年です。今年は最後の稲刈りまで水分が下がりませんでした。米の保存のためには15%以下まで乾燥させなければなりません。乾燥温度を上げると時間は短縮できるのですが高温乾燥は食味が落ちるので時間をかけてゆっくり乾燥。すると乾燥機が空かないので稲刈りができません。適期刈り取りの為に、朝露がまだ落ちる前から機械に詰まらないよう低速でゆっくり刈り取りとか乾燥機が夕方に空くのに合わせてコンバインにライトを点けて刈り取りとかちょっとした時間を見つけての作業でした。苦労のかいあって適期に刈り取りでき、良いお米が収穫できました。
連日報道されているお米問題。政府は備蓄米放出とアメリカ米の輸入前倒し。民間では外国米輸入。農水大臣は米流通を「市場にジャブジャブ」という表現を使い価格を下げる政策をとると発言しました。「平成のコメ騒動」から30年。米価格は年々下がり、米作りは自給0円と言い表されました。価格が安い時には国は「市場原理」と傍観し、価格が上がると備蓄米、破格の2000円での放出で市場介入。今頃になって減反政策は間違い、コメ増産と言います。今回の米騒動は国内の「需要量と供給量の実像」が把握できていなかったとうお粗末な事が原因のようですが、農家にとって供給過剰は安値、豊作貧乏につながり困ったことです。だから国が進める「市場原理」の中では何の保証もないのに余るようには作れなかったのです。
私はNHKテレビ「映像の世紀」をよく見ます。映像技術が開発され、発展していく過程でこれまで撮影され、保存されてきた映像がテーマに沿って放送されます。「歴史は繰り返す」の言葉通り私たちの身の回りで起きている現象が過去の映像の中に現れています。よく放送されるナチスドイツ。占領した国から収奪した農産物を、また若い労働者をドイツ本国に送り、国民は働かずして豊かな生活を享受する様子が流れます。日本でも高度経済成長と言われた時代、地方農村の若者が安価な労働力として、また季節出稼ぎ労働者が都会に流れることで、経済が成長しました。日本では1960年代、ついこの前まですべての国民に米が行き渡らず、「貧乏人は麦を食え」という時代だったのが、豊かになり、パンや麵を食べるようになると米は余るようになりました。国は市場経済に委ねるとして米流通から手を引き、「民間自立」の時代になりました。全国各産地は米が余って売れない中で収量が多い品種を捨て、味が良い品種を作り「どうぞうちの米を買ってください」と頭と価格を下げて商売をしてきたのがこの30年です。ドイツに占領された国は食料を、また来年撒く種まで収奪されました。現代日本では買い手市場の中で地方農村は体力を奪われ老夫婦の生活が精いっぱい。後継者を育てる力など残っていないのです。社会的強者と弱者の関わり合いの中で生産現場を知らない「都会の民」の生活の為に「農村の民」は収奪されSDGsの時代にコメ生産農家は消滅危惧種になろうとしているのが現実です。
我が家の菜園では沢山の生き物がそれぞれけん制しあいながらもバランスよく暮らし、野菜は健康に育っています。人間の世界でもそれぞれの生存を尊重しあうことが明日の自分の生存につながる最低限の姿勢ではないでしょうか。